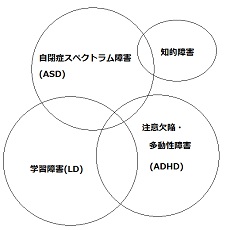星野源は「子犬の目をした脅迫者」? 『逃げ恥』が描いた、普通の人々の「普通じゃない」美しさ
――女性向けメディアを中心に活躍するエッセイスト・高山真が、世にあふれる”アイドル”を考察する。超刺激的カルチャー論。
TBS系ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』HPより。「親子や兄弟姉妹ですら合わない部分があるのが当然なのだから、違う家庭で育ってきた者同士が合わない部分があるのは当たり前。そんな『当然』や『当たり前』を、『困る』とか『つらい』に変換するクセがついてしまうと、ふたりの間にあるパワーを奪ってしまう。そんなもったいないことって、ない」
「それを踏まえたうえで、ふたりで、たくさん話し合いましょう『どちらかが折れることを前提とした話し合い』ではなく、『どちらの望みもある程度取り入れるための話し合い』をね」
「知りたい。知ってもらいたい。その努力を惜しんだら、おしまい」
「面倒くさいといえばそのとおりかもしれないけれど、それは新しい人間関係を構築する際、避けては通れない面倒くささだと思います」・・・・・・・・・・・・
上の文章は、今年発売した私の本『恋愛がらみ。 ~不器用スパイラルからの脱出法、教えちゃうわ』(小学館)からの、ほぼ原文の写しです。手前味噌の極みと思われても仕方ないオープニングで恐縮です。私の本は、『Oggi』というファッション誌で10年ほど連載していたエッセイから「恋愛がらみ」に特化したものをまとめたものでして、写した文章は、だいたい3~8年前くらいに『Oggi』にて最初に発表したものではなかったか、と記憶しています。
本当に僭越極まりないのですが、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系)の最終回を見ながら、「ああ、こういうこと書いてたわ」と思い返していました。
それにしても本当に面白いドラマでした。ラブコメドラマ(要するに「ハッピーエンドで終わらせることが至上命題」のドラマ)の最終回で、これほどまでに「めんどくさい」「面倒」という単語が出てきたドラマは、いままでになかったと思います。
最終回の1つ前の回で、平匡は「脱・童貞」を果たし、何やらおかしな方向に進んでいきました。「かわいい嫉妬」の体をとってはいましたが、みくりの仕事先のひとつをぶった切る。「異性が働いている場所でバイトなんかすんな」とか言って、恋人の経済のヒモを切っていくような精神的童貞や処女はけっこういます。しかし、それを35歳の平匡がやるようになるとは。平匡本人がどんなに多忙であっても、「家事のプロ」としてみくりが作ったおかずが大失敗に終わっても、料理にはきちんとポジティブな感想を出していたのに、「美味しい」とも言わなくなる。そして、「みくりが『対価の発生する、仕事』だからこそ完璧にこなしていた」家事全般を、「無償のもの」として計算し、ライフプランを立てて、ドヤ顔のプロポーズをカマす…。そんなとんちんかんなドヤ感たっぷりの提案にみくりが異議を申し立てれば、自分が悪手ばかりを打っていることに気づかないまま、「みくりさんは、僕のことが好きではないということですか?」(訳/僕のことが好きなら●●してくれるものじゃないの?)と、子犬の目で恫喝にかかる…。ええ、あれは「子犬の目をした脅迫者」としか言えない表情でした(星野源、まったくうなってしまうほどの名演です)。そのシーンの20~30分ほど前、「平匡さんは、可愛すぎる」「可愛いは最強です。可愛いには絶対服従です!」と言っていたみくりが、決然と「それは、好きの搾取です!」と言い返したシーンでは、「よくぞ言った!」と画面に声をかけてしまったほどです。このシーン、ブラック企業による「やりがいの搾取」を痛烈に批評した、みくりのセリフと対になっているあたり、この作品自体の構成のうまさにも感じ入りました。
で、最終回。実を言うとこの最終回のいちばんの“ドリーム”は、「平匡が、『嫌な意味でも男になってしまった』自分自身を、序盤ですぐに反省する」という点ですが、これはこれで仕方がない。というのも、「避けては通れない面倒くささをきっちり描くためには、かなりの尺が必要である…。そんな判断を制作側がした」ということが、すぐにわかる作りになっていたからです。
CMとオープニング&エンディングを除けば正味60分を切るだろう時間の中で、制作側は、「みくりと平匡の話し合い」というか「すり合わせ会議」を、ドラマ前半の中になんと3回も入れています。そのうち1回は、家に仕事を持ち帰ったみくりがしっちゃかめっちゃかになっている状態のとき。そんなときであっても、「話し合い」「すり合わせ」は必要である、という根幹から、このドラマは逃げていなかった。
他人と関係を結んでいくのは、それが「結婚」という形をとっていようといまいと、本当にめんどくさい。当たり前のことだから、つらかったり困ったりということではないけれど、ものすごくめんどくさい。そんな厳然たる事実を、パロディを使ってポップに演出してはいましたが、正面切って描いていた。それだけでも称賛に価するドラマだったと私は思います。
当然、どちらか一方がしっちゃかめっちゃかなときは、ただでさえめんどくさい「話し合い」なんて、うまくいくはずがありません。みくりは、平匡に投げやりな態度で「(この関係を)やめるなら、いまです」みたいな捨て台詞を吐き、家での仕事場所(浴室)にこもって扉を閉めてしまいます。
それに対し、平匡は、「いままで自分は、周囲に壁を作っていたけど、いまはみくりさんが、それをしている」「自分の壁をノックしてくれたみくりさんに、いま自分ができることは…」と心の中で回想し、みくりがこもる浴室のドアをノックし、扉を開けないまま、話し出すのです。
「生きていくのって、めんどくさいんです。それはひとりでもふたりでも同じで、それぞれ別のめんどくささがあって。どっちにしてもめんどくさいんだったら、一緒にいるのも手じゃないでしょうか」
「みくりさんは自分のことを普通じゃないと言ったけど、僕からしたら、いまさらです。(中略)世間の常識からすれば、僕たちは最初から普通じゃなかった。いまさらですよ」
そう言いながら、浴室の扉にかけた平匡の手は、その扉を開けることなく、平匡は静かにその場を離れます。
平匡のモノローグは「みくりさんは僕が作った壁をノックしてくれた」的なものだったのですが、実のところ、みくりのノックとは、初期~中期の平匡にとってはむしろ「壁を蹴破る」くらいの勢いのものでした。
「結婚してよ!」
「私の恋人になってもらえませんか?」
「スキンシップはどうでしょう?」
「バカ!」
「いいですよ、そういうことしても(←平匡にとって人生初のセックスのお誘い)」どれもこれも、「童貞の壁」(しかも35歳)を粉々にする破壊力だったことでしょう。対して、平匡のノックは、文字通りの「ノック」であり、それも「扉を開けない」「壁は破らない」繊細さを持ったものでした。「女子の心の壁を破壊して、その心に入りこんで来るパワーを持つ男子」と、「心の壁を破られ、交際を始めて、つきあいが深まるにつれ徐々に男子のパワーの中に繊細さを加味していく女子」の組み合わせがそのほとんどを占める日本のラブコメ作品において、それは明らかに「普通じゃなかった」のです。「普通じゃなかった」のは、単に「ふたりは契約結婚からのスタート」ということだけではなかったわけです。
冒頭に続き私個人の話をして恐縮ですが、私は初恋のときから、自分が「普通じゃない」ことを自覚していました。ドがつく田舎に生まれたゲイで、初恋は35年以上前のことでしたから。そこからは「普通でない自分」をいかに受け入れ、その次は、そんな自分を受け入れてくれる他者(性愛の相手であれ、友情の相手であれ)をいかに探すか、という道を歩いてきたのです。そして、私はこのドラマで、「ノンケの男女の相当数もまったく同じことをしている」ということを、あらためて確認した思いです。
みくりは、「こざかしくて、めんどくさい女」という自己イメージ(明らかに「私フツーに女らしくないでしょ」という自己認識です)ゆえに、自分自身にどうしても低い点数をつけてしまう人間だった。平匡は、「ゲイはイケメンとみたら誰彼かまわず襲いかかる」「ゲイは男性の目線と女性の目線をあわせもつ」みたいな偏見丸出しの分析をしながらも、自分の分析をされるとムッとし、そしてムッとする自分自身の器の小ささ(明らかに平匡が「男らしさ」と形容しているだろう性格の対極にあるものです)に悩む日々が続く。ま、救いなのは、そんな自分の偏見や器の小ささを反省し、即座に成長の跡を見せることですが。ちなみに、「男目線」とか「女目線」とか、そんなものはありません。そんなザックリしたものは存在しないし、ヘテロであろうとゲイであろうと、個人個人が持っているのは「私の目線」「僕の目線」だけです。そういうことを、このドラマで風見(人間関係の機微をきちんとわかっているが、ややいたずらが過ぎるイケメン)がきちんと言及していたのには目を見張りました。
また、石田ゆり子演じる、みくりの伯母・百合(ゆりちゃん)は、若さを武器に自分に牙をむく20代中盤の女子に、「多くの女性にとって、『加齢は不幸でしかない』という『普通』が、女性たちの呪いになっている」という現実を指摘しながら、「あなたがいま『価値がない』と切り捨てたものが、あなたの未来になるなんて、そんな恐ろしい呪い(要するに、普通)からは、さっさと逃げてしまいなさい」と優しく諭す。しかし、そう言いながらも百合は、自分のほうが17歳年上である風見との恋愛に、「普通の価値観」にとらわれてギリギリまで踏み出せなかったりする(最後に踏み出せて、ゆりちゃん自身も呪縛から解き放たれて、本当によかった)。
ゆりちゃんの部下である若い女性・堀内は、アメリカからの帰国子女であるがゆえに、「普通の日本人」「普通のアメリカ人」からはみ出してしまう自分自身を自覚しつつ、自分自身をはみ出させようとする「普通の日本人像」と戦っている。同じくゆりちゃんの部下である若い男性・梅原は、ゲイであるがゆえに「普通のノンケの男女」からはみ出している自分を自覚している。そして「ノンケの普通」が回している「この世界の日常生活」では会えないからこそ、ゲイの出会い系アプリを使う。「普通のノンケの男女」に対する嫉妬も認めている。会社の人間関係でカミングアウトをするのは、心から信頼した堀内だけ。その堀内にも、「ナイショな」と、アウティング(自分の望まない人間関係にまで秘密をバラされてしまうこと)に対する牽制を忘れない。「普通じゃない」ゆえに、そこまで周到なことをしなくてはいけないことを、骨身に染みてわかっている。まだ見ぬ意中の人・沼田と出会った瞬間、その場に居合わせた、信頼する上司のゆりちゃんにもカミングアウトしたのも同然なのですが、ここにゆりちゃん以外の会社の人間がいたら、梅原は、沼田の前でまったく素知らぬ顔をしただろうと断言できます。
男だろうと女だろうと、ノンケだろうとゲイだろうと、何歳であろうと、どんな人生を送っていようと、誰もがそれぞれに「普通じゃない」部分を抱えている。平匡が最終回で「僕たちは最初から普通じゃなかった」と気づき、風見は第4話だったかな「普通って誰が決めるんだろう。くだらない」と口にしていたように。
それぞれの「普通じゃない」部分は、当然、それぞれに違っています。そして、「それぞれに違っている部分」それが、個性になる。「それぞれに違っている部分」こそが、多数決でなんとなく決められてしまっている「●●らしさ」(●●には、男とか女とかオジサンとかオバサンとかノンケとかLGBTとか日本人とか、とにかく好きな単語を入れてOK)ではなく、「自分らしさ」になる……。そのことをこれだけはっきり言い切った日本のドラマを、私はほかに知りません。
お互いの「普通じゃない」を認め合うこと。認め合ったうえで、めんどくさいことから逃げずに、ノックし合うこと。そして、変わりゆく関係性に対して敏感であろうと努めること。コミュニケーションの本質は、まさにそこにあると私は思っています。ええ、ドラマが言う通り、それは本当にめんどくさい。でも、そこから逃げなかったふたりだからこそ、逃げなかった平匡だからこそ、みくりは、最終回のいちばんの盛り上がりどころで、ようやく平匡に「大好き」と言えたのです。「大好き」と伝えたあとも、「(ふたりの関係性の)模索は続きます」と言い切る平匡だからこそ、みくりは、さまざまな未来の可能性を(妄想の中ではありますが)楽しみにできるのです。
すべてにおいて「普通」な人が誰ひとりとして存在していないこの社会。すべての「普通じゃない」人にとって、本当に優しい、素敵なドラマでした。2016年も終わりますが、この時代にこういうドラマが出てきたことを、私は素直に喜びたいと思っています。
高山真(たかやままこと)
男女に対する鋭い観察眼と考察を、愛情あふれる筆致で表現するエッセイスト。女性ファッション誌『Oggi』(小学館)で10年以上にわたって読者からのお悩みに答える長寿連載が、『恋愛がらみ。 ~不器用スパイラルからの脱出法、教えちゃうわ』(小学館)という題名で書籍化。人気コラムニスト、ジェーン・スー氏の「知的ゲイは悩める女の共有財産」との絶賛どおり、恋や人生に悩む多くの女性から熱烈な支持を集める。月刊文芸誌『小説すばる』(集英社)でも連載中。